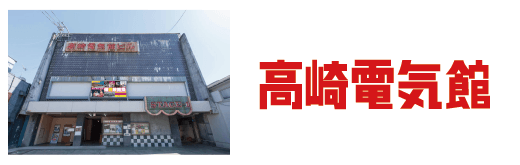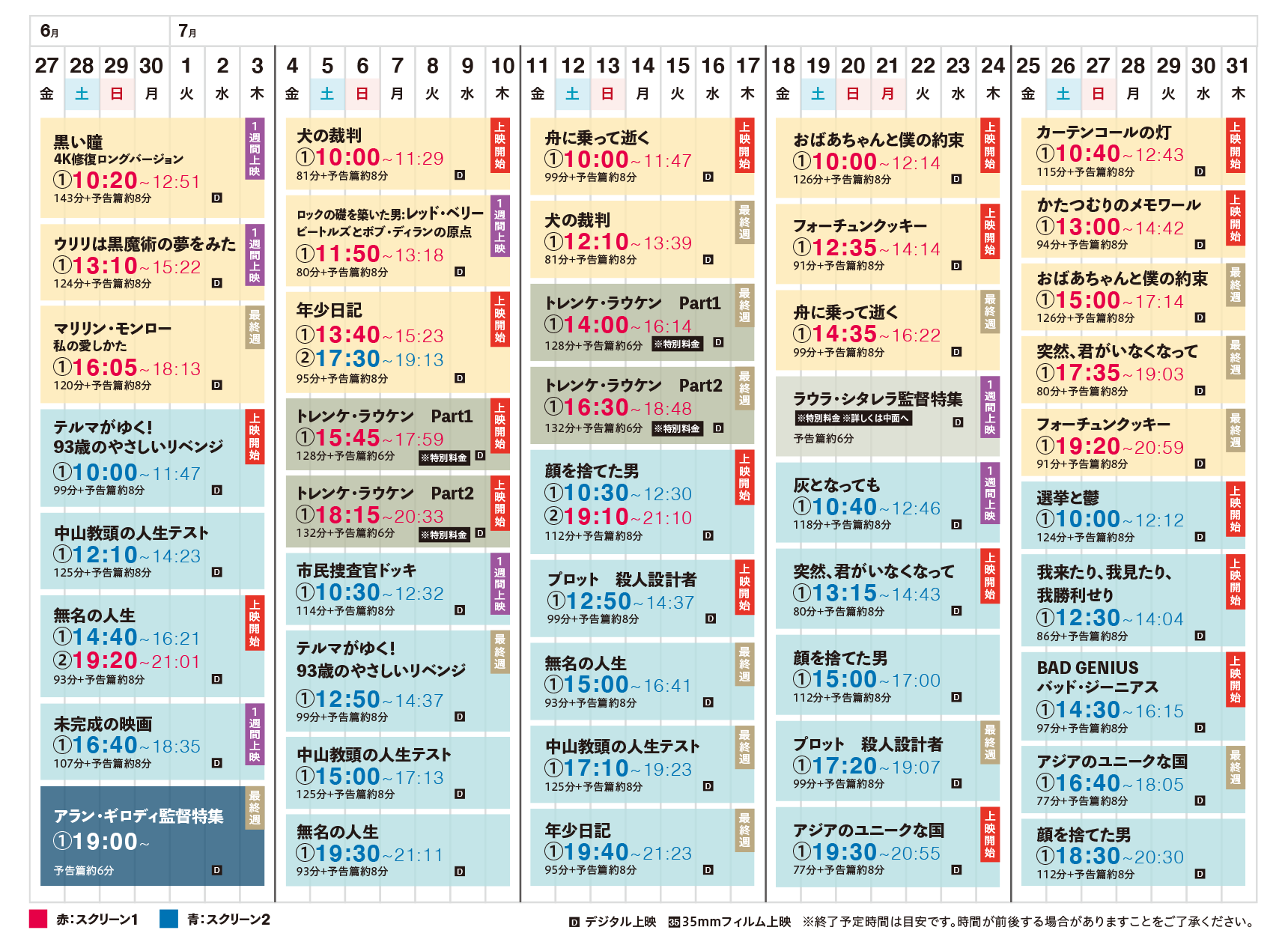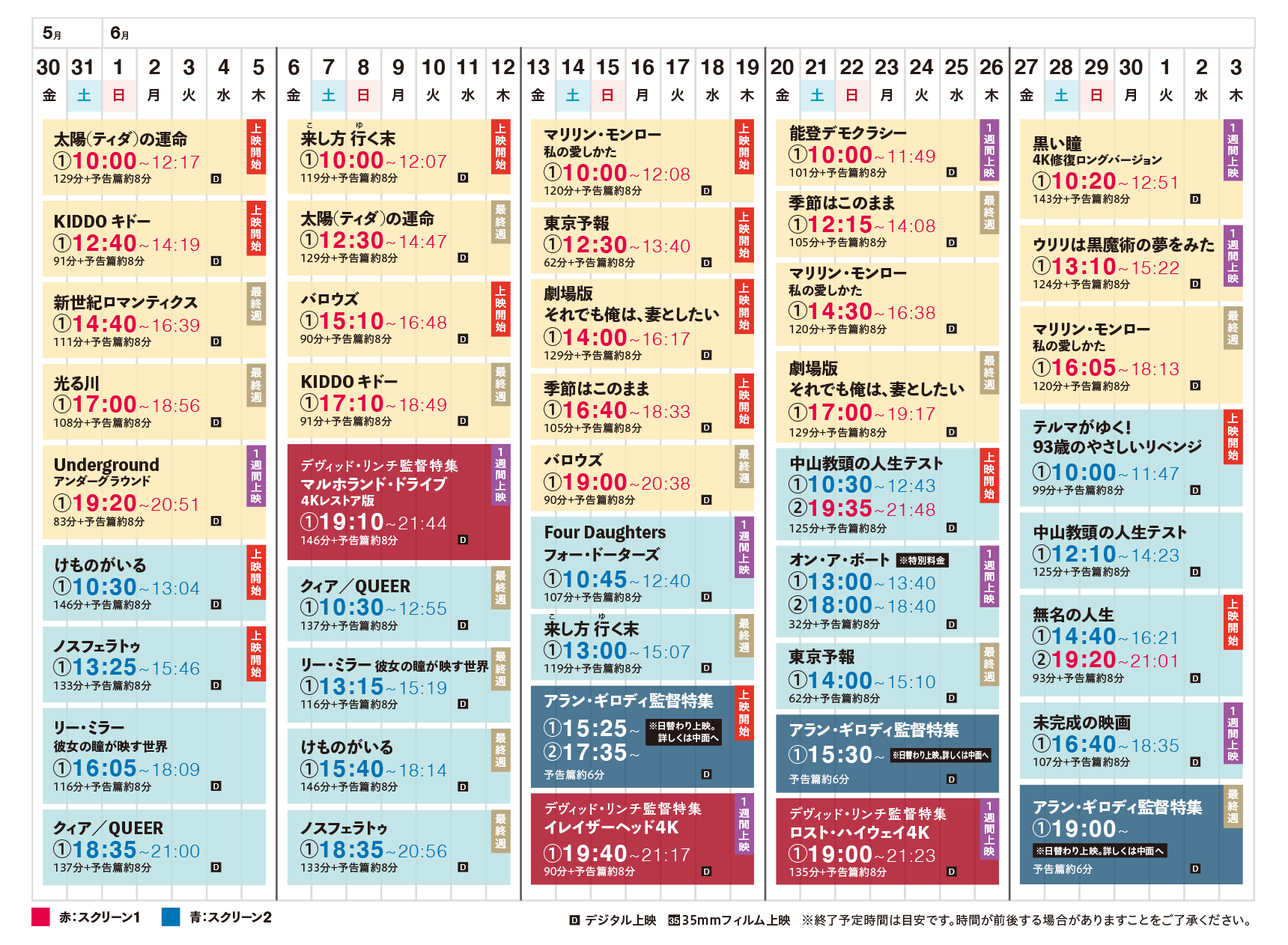上映中の作品
- 07.18 (金)
- 07.19 (土)
- 07.20 (日)
- 07.21 (月)
- 07.22 (火)
- 07.23 (水)
- 07.24 (木)
-
『おばあちゃんと僕の約束』
上映時間:126分
購入する10:00-12:14スクリーン1 -
『灰となっても』
上映時間:118分
購入する10:40-12:46スクリーン2 -
『フォーチュンクッキー』
上映時間:91分
購入する12:35-14:14スクリーン1 -
『突然、君がいなくなって』
上映時間:80分
購入する13:15-14:43スクリーン2 -
『舟に乗って逝く』
上映時間:99分
購入する14:35-16:22スクリーン1 -
『顔を捨てた男』
上映時間:112分
購入する15:00-17:00スクリーン2 -
-
『プロット 殺人設計者』
上映時間:99分
購入する17:20-19:07スクリーン2 -
-
『アジアのユニークな国』
上映時間:77分
購入する19:30-20:55スクリーン2 -
-
『おばあちゃんと僕の約束』
上映時間:126分
購入する10:00-12:14スクリーン1 -
『灰となっても』
上映時間:118分
購入する10:40-12:46スクリーン2 -
『フォーチュンクッキー』
上映時間:91分
購入する12:35-14:14スクリーン1 -
『突然、君がいなくなって』
上映時間:80分
購入する13:15-14:43スクリーン2 -
『舟に乗って逝く』
上映時間:99分
購入する14:35-16:22スクリーン1 -
『顔を捨てた男』
上映時間:112分
購入する15:00-17:00スクリーン2 -
-
『プロット 殺人設計者』
上映時間:99分
購入する17:20-19:07スクリーン2 -
-
『アジアのユニークな国』
上映時間:77分
購入する19:30-20:55スクリーン2 -
-
『おばあちゃんと僕の約束』
上映時間:126分
購入する10:00-12:14スクリーン1 -
『灰となっても』
上映時間:118分
購入する10:40-12:46スクリーン2 -
『フォーチュンクッキー』
上映時間:91分
購入する12:35-14:14スクリーン1 -
『突然、君がいなくなって』
上映時間:80分
購入する13:15-14:43スクリーン2 -
『舟に乗って逝く』
上映時間:99分
購入する14:35-16:22スクリーン1 -
『顔を捨てた男』
上映時間:112分
購入する15:00-17:00スクリーン2 -
-
『プロット 殺人設計者』
上映時間:99分
購入する17:20-19:07スクリーン2 -
-
『アジアのユニークな国』
上映時間:77分
購入する19:30-20:55スクリーン2
-
『おばあちゃんと僕の約束』
上映時間:126分
購入する10:00-12:14スクリーン1 -
『灰となっても』
上映時間:118分
購入する10:40-12:46スクリーン2 -
『フォーチュンクッキー』
上映時間:91分
購入する12:35-14:14スクリーン1 -
『突然、君がいなくなって』
上映時間:80分
購入する13:15-14:43スクリーン2 -
『舟に乗って逝く』
上映時間:99分
購入する14:35-16:22スクリーン1 -
『顔を捨てた男』
上映時間:112分
購入する15:00-17:00スクリーン2 -
-
『プロット 殺人設計者』
上映時間:99分
購入する17:20-19:07スクリーン2 -
-
『アジアのユニークな国』
上映時間:77分
購入する19:30-20:55スクリーン2
-
『おばあちゃんと僕の約束』
上映時間:126分
購入する10:00-12:14スクリーン1 -
『灰となっても』
上映時間:118分
購入する10:40-12:46スクリーン2 -
『フォーチュンクッキー』
上映時間:91分
購入する12:35-14:14スクリーン1 -
『突然、君がいなくなって』
上映時間:80分
購入する13:15-14:43スクリーン2 -
『舟に乗って逝く』
上映時間:99分
購入する14:35-16:22スクリーン1 -
『顔を捨てた男』
上映時間:112分
購入する15:00-17:00スクリーン2 -
-
『プロット 殺人設計者』
上映時間:99分
購入する17:20-19:07スクリーン2 -
-
『アジアのユニークな国』
上映時間:77分
購入する19:30-20:55スクリーン2
-
『おばあちゃんと僕の約束』
上映時間:126分
購入する10:00-12:14スクリーン1 -
『灰となっても』
上映時間:118分
購入する10:40-12:46スクリーン2 -
『フォーチュンクッキー』
上映時間:91分
購入する12:35-14:14スクリーン1 -
『突然、君がいなくなって』
上映時間:80分
購入する13:15-14:43スクリーン2 -
『舟に乗って逝く』
上映時間:99分
購入する14:35-16:22スクリーン1 -
『顔を捨てた男』
上映時間:112分
購入する15:00-17:00スクリーン2 -
-
『プロット 殺人設計者』
上映時間:99分
購入する17:20-19:07スクリーン2 -
-
『アジアのユニークな国』
上映時間:77分
購入する19:30-20:55スクリーン2
-
『おばあちゃんと僕の約束』
上映時間:126分
準備中10:00-12:14スクリーン1 -
『灰となっても』
上映時間:118分
準備中10:40-12:46スクリーン2 -
『フォーチュンクッキー』
上映時間:91分
準備中12:35-14:14スクリーン1 -
『突然、君がいなくなって』
上映時間:80分
準備中13:15-14:43スクリーン2 -
『舟に乗って逝く』
上映時間:99分
準備中14:35-16:22スクリーン1 -
『顔を捨てた男』
上映時間:112分
準備中15:00-17:00スクリーン2 -
-
『プロット 殺人設計者』
上映時間:99分
準備中17:20-19:07スクリーン2 -
-
『アジアのユニークな国』
上映時間:77分
準備中19:30-20:55スクリーン2
近日上映予定作品 Coming soon
知らなかった“世界”と出会う場所
映画を通して新しい世界と出会い、日常の景色を少しでも豊かに感じることができますように
2つのスクリーンで世界中から選りすぐりの映画を日々上映しています。